政治の危機。
それは社会が複雑化したことの必然的な帰結だ。全部を視野に入れるには、この社会はあまりに複雑すぎる。かなりの時間と脳内リソースを払ってまで、わざわざ政治に参加したいとあなたは思うだろうか?
情報過多の世の中で、今価値のあるものは「情報を減らせるもの」だ。GoogleでもTwitterでもなんでもいい。要は、ネットの大海から、自分が欲しいと思う情報をたった6インチの画面に絞ってくれるツール。そこに政治的=不要な情報が入る余地は少ない。つまり政治はもはや欲望されなくなってしまった。
そんな状況で、新時代の民主主義、政治はどうあるべきか。
今回紹介する本は、東浩紀さんの著した「一般意志2.0」だ。
(2025/9/23:この1年で政治が大きく変わった状況を踏まえてこの記事の最後に追記を加えました)
まさかのルソー
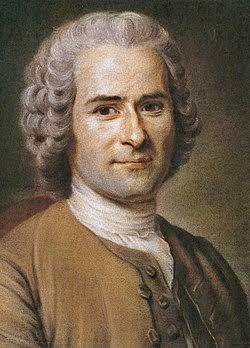
ルソー。中学で社会契約説を習って、それっきり。そんな人も多いんじゃないだろうか。「民主主義の基礎を築いた人」なんて紹介をされることもある。だがそれは少しの嘘を含んでいる。だって本人は「国や風土によっては独裁だってアリ」「国民はどんな命令であろうとも、一般意志に従わきゃいけない」「政治にコミュニケーションは要らない」と主張しているのだから。
一方、ルソーは恋愛小説から教育論まで幅広い著書を残していて、そこでは個人の自由を奨励している。自由と全体性、個人と政治のこの対立をどうまとめるか。通常、ルソーには文学者としての側面と社会学者としての2つの側面があって、分裂していた、として解釈される。
この矛盾をどう解決するか。
ルソーの思想に少し踏み込むと、彼は政治は一般意志を前提として動かされるべきだと主張した。
一般意志。個人個人が皆まとまったときの、全体の利害に関する、全体の意志である。(追記による補足:私のイメージでは「税金」なんかがまさに一般意志的な存在だ。各個人のレベルでは、皆払いたくないと思っているため、単にその意志の総和を取っただけ(=全体意志)では、税金廃止が国民の総意ということになってしまう。だがむしろ一般意志はそうした意向に反して、皆のためという観点に基づいた集団全体の意志である。…このルソー解釈がどこまで正しいかは保証しかねるけど)
そして一般意志は政府の上に立つ。国民が一般意志を作り、政府は一般意志に従い、国民は政府に従う。ルソーは、このような循環的システムを理想とした。そして彼は、「国民は一般意志に従うべきだ」とした。「一般意志に従え」は「時の政府に従え」とは異なる。このシステムは、国民全体の意志にそぐわない政府を解約すること、つまり革命を認める。だから通常の社会契約説(ホッブズとかロックとか)とよく一緒にされる。
ところが、である。『一般意志2.0』では異なる指摘がされている。
一般意志とはなにか。東浩紀によると、一般意志=無意識の欲望であるらしい。そして一般意志2.0においては、それをデータベースとして捉えることができる。人々が集まって、個人個人の欲望を持ち寄ることで、政治が実現される。
はい?
個人個人が、政治的意見じゃなくて、単なる欲望を持ち寄って、政治が実現するわけないじゃんか。
実現できる、らしい。
これは僕のイメージだが、アダム・スミスの「見えざる手」みたいな役割なんじゃないだろうか。資本主義は市場原理に従う。すると、個人個人の「売りたい」「買いたい」という私的な欲望が集まる。結果、需要と供給は調整され、適正な価格に落ち着く。(ミクロ経済学ではこの価格が社会的余剰を最大化する、最適解となるらしい)。誰も社会全体のことを考えなくても、勝手に「政治」が行われている例と言えるだろう。
技術革新の効果
長らく、一般意志は論理的必然性からうみだされただけの、実現不可能なものだと考えられてきた。だけど今、時代は変わりつつある。一般意志は、言ってしまえば「場の空気」なのだが、情報技術革新で、それを可視化できるようになった。
東さんいわく、たとえば、予測変換。皆が勝手に入力した単語が、結果として予測精度を高める。同じように頻度分析を用いて、ネット上で、どのような単語が政治的文脈で多く使われているか。そういう「何気ない発言」を可視化することで、場の空気は存在できるようになるのだ。
さて、無意識が政治を先導する、という旨をずっと書いてきた。だが実際に東が考えるのは、意識と無意識それぞれが、互いを補い合う政治だ。
技術革新による「新しい民主主義」なんていうと、だいたい、二つのパターンに収束する。
①電子投票とか、直接ネットを政治につなげて、あくまでも<政治>主導の政治。
②アルゴリズムのように情報をインプットすることで、全自動で行われる政治。
一般意志2.0が目指すのは、その両者である。実際には官僚や政治家が話し合うのだが、それを配信して、コメントのフィードバックの分析を可視化する。政治版<ニコニコ動画>。そう、実際に政治を行うのはあくまで為政者自身である。だけど<聞き流す>ように政治を視聴する視聴者の、その何気ないつぶやき(一般意志)によって、その恣意性を制限しようというのだ。
一般意志は、あくまで制約。「これはやっちゃいけないよ」というネガティブな制約である。いや、為政者自身その道を進もうと思えば進めるのだが、実際に目に見えるカタチのフィードバックを無視するというのは、相当な勇気(蛮勇?)と確信が無いとできないだろう。
逆にそうすることによって、「民主主義2.0」はポピュリズムを回避できる。いや、正確にはしやすくなる。こんなあいまいな表現に逃れたのは、人々がTwitterやSNSで、今後ますますおしゃべりになっていく時代の趨勢を逃れることはもはや不可能だからだ。
ノートの罫線みたいな政治だ、と思った。ルーズリーフに文字を書くとき、罫線を無視しようと思えば無視できるのだが、ついつい線に従って文章を書いてしまう。民衆の無意識をガイドとして、あくまでも主導するのは政治だが、でも民意からかけ離れることを防ぐ。そういう方向性。

20世紀的「新しい民主主義」の欠点
これまでの政治哲学で掲げられてきた、「新しい民主主義」は、人々の徹底的な話し合いによって妥協点を探ろうという<熟議民主主義>であった。ハンナ・アーレント、ハーバーマス。彼女ら彼らの主張も、結局はそういうこと。たしかに、それは「理想」である。
だが、実現不可能の「理想」に過ぎない。
どういうことか。
しばしば熟議民主主義の欠点として挙げられるのは、参加コストの高さ、である。とんでもない。欠点の一つどころかそれが全てだ。
熟議=徹底的な話し合いなのだから、その参加者には必然的に多くの知識が要求される。分野が高度に専門化して、政治全体を見通すことが不可能になった現代において、である。そして今の一般的な若者は、世の中全体を見通す視野を持とうとしていない。(『動物化するポストモダン』)
そもそも話し合いで妥協できるのは、互いに共通認識を持っているときだけだ。最低限「合意すべき」くらいの意識が無いと、分かり合うことは不可能だ。ネットという一回性の他者が現れては消える場に、そのような話し合いを求めることは、無駄である。
政治が機能しなくなるのも、必然である。
20世紀の思想は、第二次世界大戦の狂気を経て、あまりに反動的になりすぎた。理性を過大評価しすぎた。だが実際、人は無意識を制御できるものでは無い。むしろ民主主義を保つためには、意識と無意識の2つのレベルで政治が繋がってなくてはならない。
熟議は、参加者同士で、閉じてしまう。
連帯の可能性
「<公>の場では、政治、正しさ、社会について語るべきでは無い」ーそう言った思想家がいた。ローティーという人である。
これはちょっとショッキングかもしれない。なぜなら私たちは普通、私的な場では私的な快楽に耽ること(=動物化)が許されるが、公的な場では清く正しく<政治的>であらねばならないと信じているからだ。
だがローティはこの信念を逆転させる。「善を語るのは、プライベートでのみ許される。」
どういうことか?
相対主義的に考える。あらゆる主義、主張は、それぞれ一面的に正しい。ならばどれだけ話し合っても究極的に解決することはない。自分の信じていることが偶然的であり、異なる信念も同様に存在していいと認めること、自己矛盾に耐える力こそが新時代の倫理の基盤になる。彼はそう考えた。
自分は神を信じつつも、別の神を信じる他者、そもそも神を信じない他者と対話を続けること。これが最も難しい。この自己矛盾に耐えようとする態度を彼は<アイロニー>と呼んだ。
この<アイロニー>の態度を機軸に据えた、公共空間の原理を考えることができる。ローティは、社会の連帯の可能性を「想像力」に見出した。考えてみれば当たり前だ。論理による連帯は不可能と、彼自身が割り切ったのだから。
想像力は人間だけに備わるものでは無い。理性という<人間>の側面から、<動物>的な面に焦点を当てた、社会。見知らぬ他者への偏見は無くならず、友愛を基礎に据えることもできないが、目の前の他者の苦しみを前にして「苦しいのですね」ということで、人は連帯できる。
これまでの考えでは、感情は社会を分断し、理性によって溝を埋められる。そう捉えられてきたが、ここに来てようやく、感情こそが連帯を生み出すものとして、感情>理性と逆転されたのである。
新時代の社会=連帯とは、そのようなものなのかもしれない。
ネットワークの可能性
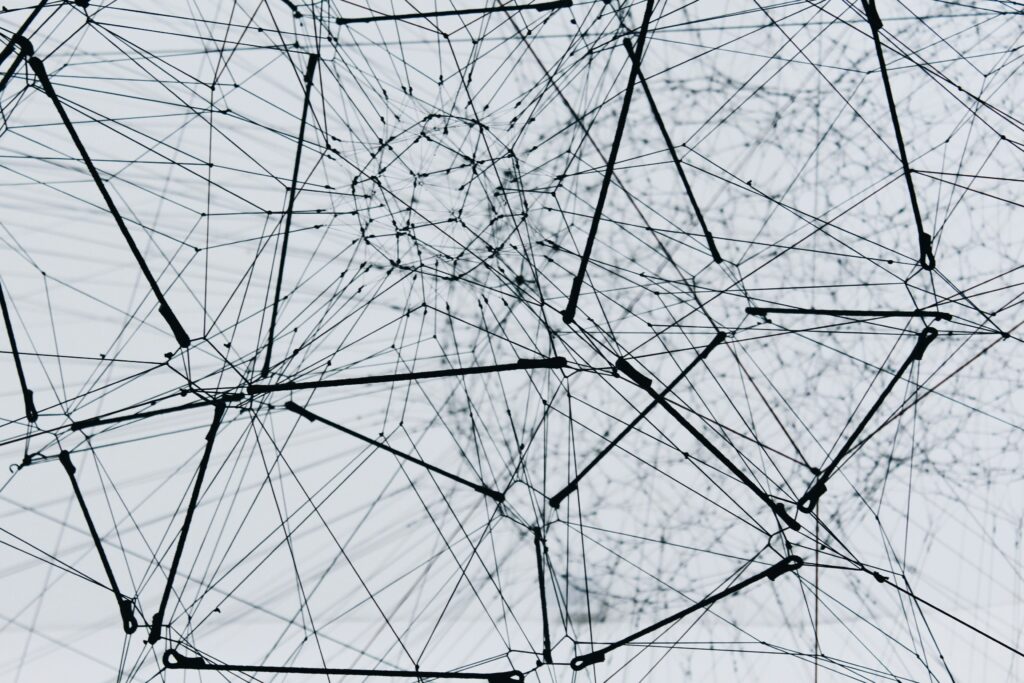
ローティの話が少し長くなってしまった。単に私が衝撃を受けた考え方だったから、フォーカスを当てすぎちゃったかもしれない。
感情によって、想像力・共感によって繋がる社会。
これ、実はルソーの考えていたことでもある。ルソーは、人々は「憐れみ」によって繋がると考えていた。目の前の苦しんでいる人を無視できない。だから仕方なく助け合ってしまう。ルソーの<社会契約説>とは言うが、その実、社会契約は、人間の本能・「弱さ」によってなされると主張していたのである。
これは、ホッブズやロックの社会契約説が、あくまでも理性を中心に契約を結ぶと考えていたのとは、対照的だ。
新しい社会はどうあるべきか。
著者の東浩紀は、Twittetのようなネットワークに連帯のモデルを見出していた。そこでは原則的に、自分の見たいものだけを見ることができるのにも関わらず、見たくないものも他人のリツイートによって視界に入ってきてしまう。
普段は共感ベースに自分の<島宇宙>に閉じこもっていても、時には<事故>のように他者とぶつかり、瞬間的に驚き、思わず自分もリツイートしてしまう。その<事故>こそが、ほかの共同体との繋がりを生み出すのである。
熟議で閉じた無数の島を、感情の糸が結ぶ。一般的な「誰か」じゃない。目の前の他者について考えることで、社会は連帯していける。政治はやっていける。
追記:昨今の政治情勢を踏まえて(2025/9/23)
実はこの文章を書いたのは1年前。追記、と言っても1年間下書き状態で放置してきたのだから、厳密な意味での追記では無いのだけれども、この1年間でいろんな変化があった。特に政治においては、兵庫県知事の齋藤元彦氏の騒動、参政党の出現。元迷惑YouTuber、へずまりゅう氏が市議会議員になったり。再生の道の一時的なブームと凋落なんかもあった。(私個人としては、当時は新しい風に乗って、政治をなんとかしてくれるんじゃないかという淡い期待もあった。途中から雲行きが怪しくなり、結果としてはAIを党首に据えた軽佻浮薄な政党に成り下がってしまったわけだが)
一言で言えば、ポピュリズムの台頭である。ポピュリズムとは、政治構図をわかりやすく単純化することで大衆からの支持を得ようとする政党だ。参政党では外国人や移民。へずまりゅう氏については鹿をいじめる中国人とメガソーラー。まさに、カール・シュミットの言う通り。政治が敵と味方を分断している。
そう思うと冒頭の1文はあやまりだ。人は複雑な政治をもはや欲望しなくなったのではない。行き場を失った善への意志のはけ口として、単純化された政治を欲望するようになった。
もちろん私はそのことについて直接に批判しようとは思わない。そもそも私にはその資格が無い。ポピュリズム批判もまた、ポピュリズムに加わる愚かな人/そうでない賢い人、という風に単純化を伴う。また、それらの主張のほとんどに合理的解決を生むような意義に乏しいとはいえ、そのような主張が生まれたこと自体がひとつの現代の状況を表していて、どうしようもない社会的不安はやはり存在しているのだから。
見ている限り思うのは、おそらく政治に関する議論の場が圧倒的に足りてないということ。熟議民主主義をこの本では批判していたが、熟議とまではいかずとも気軽に政治の話をできる環境、声を届かせる環境は必要だと思う。多くの人は、政治に軽視されてるという意識から自力救済を求めるようになっているのだから。(映画「Joker」を想像してみてほしい)。外傷的絆、(トラウマ的絆)がこのような現象には近いのかもしれない。過剰流動性に対抗するために宗教が生まれるのは周知の事実だが、そのような信者集団は同じ恐怖・不安を共有し、明確な敵を名付け、一方で救済/カリスマ的リーダーを持つことで強い共依存集団を生み出す。
これが今の現状なのかも。
大きな物語の崩壊に始まるポストモダンの今において共通前提は既に崩壊してしまった。憐れみによる繋がりは果たしてどこまで妥当なのか。自分と似た存在にしか通用しない憐れみなら、それはもはや島宇宙を繋ぐ存在とは言えない。ポピュリズムはやはり不可避だと思うし、この状況でそのままニコニコ動画的な政治をまともに行える未来を、私は想像できない。
共通前提をどう取り戻すか。ココ最近の私の関心事はそれだ。私の推しの社会学者である宮台さんがそのテーマに関する研究を熱心になさっているので、私の受験後にはもっと追求してみたい。
だが、ひとつ確かな予感がある。この状況は、上からの教育や、衒学的な議論では解決しないだろう。今圧倒的に不足していて必要とされてるのは、もっと草の根の下からの改革。それをどう構想するかは、理論の領域なんだけれども。

哲学的に考えるなら、他者の思想じゃないか。二十世紀哲学を象徴する巨大なキーワードのひとつに「他者」あるいは「他者性」がある。
これは第一次・第二次世界大戦の反省から生まれたものでもある。キリスト教が、「汝の隣人を愛せ」というとき、そこには隣人に関するひとつの重要な事実が隠蔽されている。隣人は、得体の知れない、不気味な、恐ろしい存在である。得体の知れない他者を殺そうとして起きたのが、第二次世界大戦である。
他者性とどう向き合うか。
そのような哲学を徹底的に考えた人エマニュエル・レヴィナスがいる。彼はユダヤ人だが、フランス軍に従軍していたために世界大戦を生き延びたが、家族を皆亡くしてしまった。他者とどう向き合うか、という思索はそこから始まった。
詳しい部分はこの記事の目的とはそれるので(そして筆者たる私の勉強不足ゆえ)割愛させてもらう。が、彼の哲学の方向性をここに記しておくのは意義がある。
彼は顔をよく比喩に使った(レヴィナスの顔、とよく言われるほどに)。その核は、半カテゴライズ性、無限の他者性、倫理的呼びかけである。顔は、私には所有しえない。無限の表情を見せる。私には把握しきれない。それを不気味と思うがゆえに、人が壊したいと思うのは他者の顔である。顔はカテゴライズに、ラベリングに抗う。その「他者の顔」(抽象的な)による倫理を全ての哲学の中心に置こうと考えたのがレヴィナスだった。
圧縮して書いたので理解は難しいかもしれない。だが言ってることはそんなに難しくはない。
「中国人は〜」「韓国人は〜」「ムスリムは〜」という人は十中八九、リアルの中国人or韓国人をほとんど知らない。この件に限らず、逆に実物を知っている人はそのカテゴリーが無意味であることを知るからだ。なかには不愉快な人もいるかもしれないが、優しい人もいる
リアルの感覚を足場に、抽象的な概念を超えたところにひっそりと橋をかける。その点では東さんの「憐れみ」に関する話にはすごく共感する。ただその手段としてSNSは適さないと思う。(そういえば東さんの「訂正する力」を読んだが、Xは訂正には適さないと東さんも確かに言っていた笑)。なぜならSNSの根本原理はゾーニングであり、「見たいものだけを見たい人に」という思想であり、見たくないものを見ないというコントロールが過剰に効いてしまうから。そうすると、ときには鬱陶しくも越境する他者の存在を扱うには、オンラインでは厳しいのかもしれない。
大事なことは、文字の中なんかには無いのかもしれない。そういう私も、多分、全く異なる生き方をしてる人と関わったことはほとんどない。
いろんな人と話したい。そう思った。




コメント 感想をください!
ブログ更新してたので、さっそく拝見させていただきました!
ルソーの考えていた「感情によって、想像力・共感によって繋がる社会」を読んだ時に、「確かにコレ、SNS(Twitter、インスタ)みたいだなぁ…」、と思いました。
確かに、自分もポピュリズムの台頭で想起するのは参政党でしたね。
【参政党のリーダー(名前は忘れた)は、発達障害なんてものは存在しないと言っていたような…苦笑】
我々で、「他者性とどう向き合うか」をひたすら模索していきたいですね。
今回も面白かったです!!受験頑張ってくださいね!応援してますー!
早速コメントありがとう!
感情によって繋がる政治、というのは実はルソーに限らずアダム・スミスの道徳感情論など、よく言われていたことなんですよ。むしろそれが民主主義の原点、(ローティ風に言えば、民主主義の民主主義以前的な前提)なわけですけど、それがどんどん見えなくなってきてる。その前提抜きにして民主主義をご神託のように賜ることがいかに空虚か。
参政党は意見の表明ではなく、病状のような表出です。その主張そのものには意味が無いと私は思っていますが、その主張が現れた背景にはやはりそれ相応の社会的現実があるのであって、注意を向けていかないとって思います。見たいものしか見なくていい時代。そこであえて「見たくないものを見せる」ことの倫理性についてさらに考えるのもいいかもしれませんね。
(……私の祖母は、戦争や殺人事件などの悲しいニュースが流れると、すぐにテレビを切ってしまいますが笑)