今日の土曜講習の英語、最後通牒ゲームが出てきましたね。実際の人間は、経済学の考えるような完全に利己的な人間とは違う、不公平をゆるせない非合理的な生き物だ。そんな内容だったかと思います。
そしてその分野の学問として行動経済学があります。いわば心理学+経済学みたいな学問ですね。これは、普通の経済学とはまったく異なる。なぜなら、人の心理、感情をパラメーターとして考慮するから。だから一見、理論的には不完全に見えるかもしれないが実際の日常にも活きてくる、とてもおもしろい学問なんです。…めちゃめちゃ主観だけど。
さて、今回は僕が以前読んだことのある経済学の話をすこし。話す友達もあまりいないのでここに書きとめようかと思います。
行動経済学のおはなし
行動経済学は、さきほどもいったように心理に重きを置いてます。そしてそのなかには、最後通牒ゲームを説明できるようなロジックがあります。その名も「参照点」。平易なことばで言うと、比較対象、です。促そうとする行動と、対置する参照点を常に考える。たとえば、コロナ禍のとき。政府が自粛をうながすメッセージをたくさん発信していたかとおもいますが、そのコマースには心理学者・行動経済学者もかかわっている。彼らが、メッセージをより説得力のあるものにするために試行錯誤していたわけです。
たとえば、「マスクをつけて活動を自粛しよう」っていうメッセージは、コロナ前の日常を参照点としてもつ人には届きにくいです。コロナ前と比較したら自粛なんて窮屈なだけですから。だから、参照点を変える。単にマスクを着けようというのは、マスクをつけてない状態がふつうという暗黙の前提、参照点があることになる。それでは無意識的に比較をうながしてしまい逆効果になってしまうかもしれない。だからここで、「マスクを着けるのがふつうのこと」「自粛をしないで隔離される場合と比較するとマシ」というようなメッセージがいきてくるわけです。
さてここまで参照点の話をしてきました。人は比較したがる傾向にある。だからそれを逆手に取って、見えない参照点を設定し、こっそり行動を操ろうという発想なワケです。いろいろと使えますよね、友達に頼みごとをするときとか。
ナッジのおはなし
ほかにもおもしろいのがいくつかあって「ナッジ」という考え方です。これを軽く説明するなら、お金を遣わずにこっそり人を操るひと工夫、でしょう。提唱者による正しい定義によると、「選択を禁じることも、経済的なインセンティブ(動機づけ)を大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャー(設計)のあらゆる要素」です。
具体的にナニをしてるのか、と言いますと、いくつかおもしろい例があります。たとえば犬のフンについて。飼い犬のフンを飼い主が回収していかない。そんなときどうするかというと、一般的な解決策だと、注意喚起のポスターをはる・罰金の警告をする、といったところでしょう。
しかしナッジの考えを用いた解決策は、ちがう。犬のフンの周りにチョークで矢印を描いたのです。これをするだけで、罰金や賞金(?)といった経済的インセンティブなしに人の行動を大きくかえることができました。実際に京都府宇治市でこれを行い、大きな成果を挙げたため、ベストナッジ賞なるものに選ばれました。
(ほかの有名な例をあげると、男子トイレの小便器に的やハエの絵を描いたらきれいに使用されるようになった、とか)
実践的!!なコンセプトのおはなし
目立った禁止も報酬もなく、さりげなーくひとを導く。そんなナッジにはいくつかの原則があります。
①フィードバック②インセンティブ③デフォルト④構造化
①フィードバック。行動への反応を示すということです。なんかの行動をした結果、どう改善されたのか知りたいですよね。行動結果じゃなくても、ボタンが光ったり音が鳴ったりするだけでも、楽しい。そうしたフィードバックをすることで、よい行動へ導こう、ということです。
②インセンティブ。お金以外のメリットを提示することで、行動を促そうというもの。
③デフォルト。デフォルト=前提によって操ろうということ。たとえば海外では、ドナーカードはデフォルトの状態では、「臓器提供の意思あり」の状態にマルされてます。このような変更を入れた結果、臓器提供に同意する人がめちゃめちゃ増えたのだとか。自分からやるのには勇気がいるけど、最初っからそうなってるなら…っていう人が多かったんでしょうね。めちゃ使えます。(券売機の左上にいちばん売りたい商品を置いたりするのもコレかも?)
④構造化。どちらかというと単純化、と言ったほうがいいかもしれない。選択肢だったり構図を整理して、わかりやすく示そうということ。わかりやすいから選びやすい。もちろん、ほしい選択肢を選ばせるように設計します。
だいたいこんな感じ。こうした考え方をもとにナッジを設計して、行動を促し、経済学へ取り入れようとするのが行動経済学なんです。
行動経済学でずるいのは無意識に働きかけること。「こうしろ!」じゃないんです、「これやってみよっかなー」と思わせる、さりげさな。あざといですよねー。
フロイト的に言えば、無意識とは「抑圧の部屋」であり、考えることすらない安全地帯です。そこをこっそり変えてしまう。だから僕は行動経済学のキーワードは「さりげなさ」だと思うんです。いかがでしょうか?
この学問、とってもワンダフルで興味深いのでぜひ一度学んでみることをオススメします。
みんな、学んでます!(ナッジ)
では、今回はこれで。グッド・バイ!
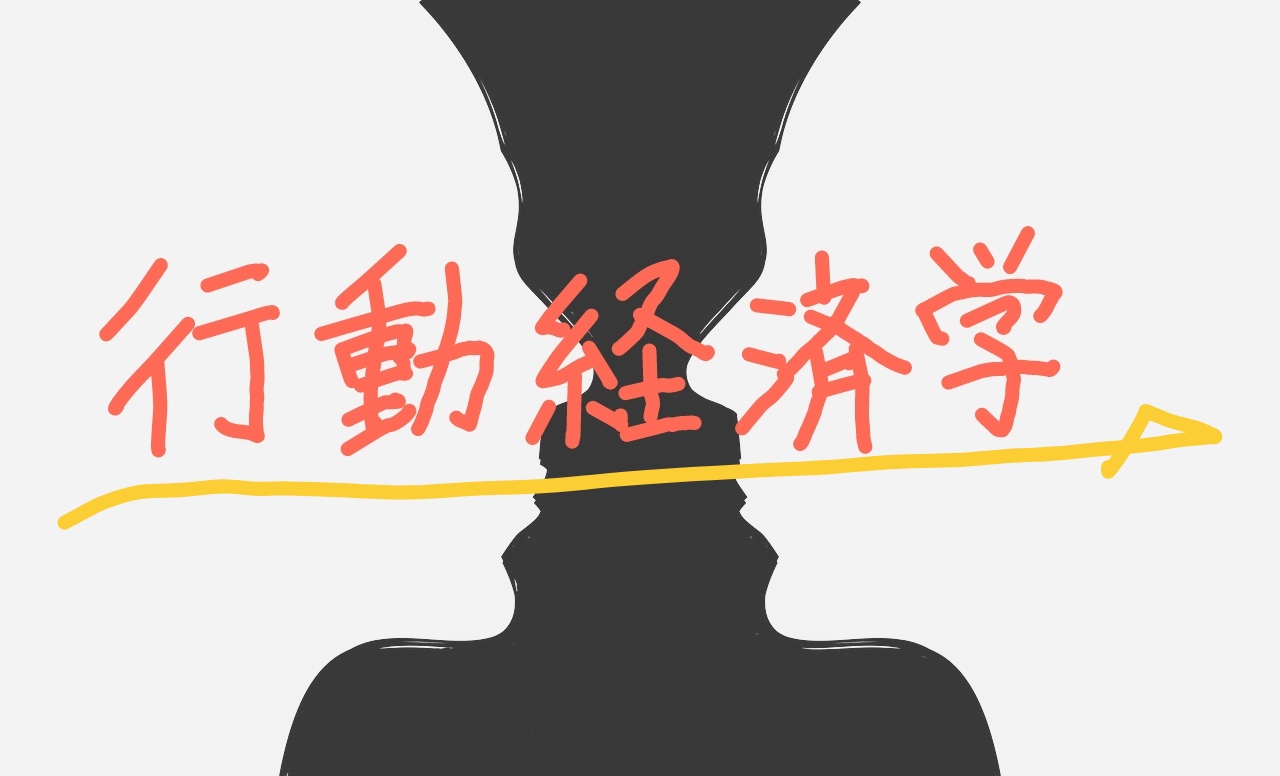


コメント 感想をください!