哲学的な問いは誰でも考えたことがあるもの。「学ぶとは」「生きる意味とは」等々。
古来から連綿と続くそのような哲学的な全ての問いかけに「無意味である」という強力な答えを用意したのが、今回読んだ『ツチヤ教授の哲学講義』です。 主軸となるヴィトゲンシュタインの考え方は非常に興味深いものなので、ぜひ読んでみてください!
今回は項目ごとに説明すると長くなるので、全部で3回に分けて投稿していきます
目次紹介
- 1日目 哲学は何ではないか
- 2日目 「我々が時計で測っているものは、時間ではない」
- 3日目 「絵が美しのは、そこに美が宿っているからだ」
- 4日目 「机の色や形は見えても、机そのものは見えない」
- 5日目 「ツチヤは、本当の意味では人間とは言えない」
- 6日目 絶対に疑えないもの
- 7日目 「われ思う」が疑えない理由
- 8日目 コーヒーを注文する方法
- 9日目 言語ゲームで哲学の問題はどう解けるか
- 10日目 「哲学の問題を全面的・最終的に解決した」究極の理論
- 11日目 哲学で世界を説明できるか
既におもしろそう(笑)
時々難しい話にはなりましたが、基本的には講義録なので説明の順序を1つ1つ追っていけば理解可能です。
ここからは内容説明になります。
1日目 哲学は何ではないか
ここで哲学について、ツチヤ教授は次のように述べています。
- 宗教は「信じる」ことが根底にあるため、哲学とは異なる。
- 文学は問題と解決がないから、哲学とは異なる。
- 科学は観測を通して事実を調べるものなので、哲学とは異なる。
なぜあえて「哲学は何ではないか」という言い回しを使ったかというと、後半で物事は解明できないと宣言しているからなんですね。
教授は随分とひねくれていらっしゃるなあ(笑)
ここで教授は哲学の問題解決について、ゼノンのパラドックスという例を挙げて説明しています。
哲学的解決をするということは誰もが認められる主張をすることである、と示しました。
ではいったい哲学は何を明らかにするのか?
その答えとして観測可能な事実を超えたもの、例えば「存在」「価値」といったもの(=形而上学的な事実)を探求する学問である、という考えがあります。例えば下にあるプラトンの考えです。
「何が善か」「何が価値あることか」といったものを知らずに、欲望に振り回されるのは人間本来の生き方ではない。観測可能な事実を超えたことにこそ本来の生き方がある。そしてそういった観測可能な事実を超えた域を探求することこそ哲学の役割である。
しかし教授は、そんな形而上学が間違っているとしました。
そして次の章からはその具体的な説に、反論をもって紹介していくというのが本書の大まかな筋です。

2日目 「我々が時計で測っているものは、時間ではない。」
ここで主に話すのはベルクソンという人の時間に関する問いです。まず時間に関してはこのような疑問が存在しています。
・そもそも時間は今という一瞬しか存在せず過去や未来も存在していないんだから、時間が存在しているとは言えないんじゃないか。
・過去も未来も測れないなら、「時間を測る」という行為も成り立たないのでは? なぜなら時間の幅を正確に測る際に、その始点も終点さえも定かではないからだ。
・私たちは時計で「時間」を測る。しかしそれはおかしなことである。なぜなら、あれはただ針の物理的な角度を測っているだけだからだ。ほかにも時間を測るとき、私たちは必ず空間を測っている。つまり私たちのいう「時間」とはさしずめ、空間化された時間である。本当の時間こそは純粋持続ある。
これに対して教授はこう反論しました。
ここでベルクソンが問題としているのは言葉の使い方、すなわち言語学上の問題であって真理について述べたものじゃない、と考えられます。なぜなら結局、時間という語の代わりに純粋持続という語を使おうという国語的な提案に終わっており、さらに私たちが時間と呼ぶものは、私たちの多くが納得している合意の上で時間としているものだから、それを「本当の時間ではない」と否定することは認められない。
確かに教授の言うことの方が妥当ですね。私個人としてはベルクソンの考えはその通りだと思いますし、結構納得しているんですけれども。

3日目 「絵が美しいのは、そこに美が宿っているからだ」
プラトン流の答え方
プラトンは原因を答えることは不可能だとしました。なぜなら(!)、「なぜ?」という問いは答えに対しても生じてしまい、完璧に疑念を取り払うことが不可能だからです。
例えば美術館に行ったとき「絵が美しいのはなぜか?」という問いが生じたとします。このとき、
⇒Q、どうしてこの絵は美しいのか?
⇒A、これこれの構図が美しいからだ。
⇒Q、じゃあなぜその構図が美しいのか?
⇒A, 黄金比が使われているからだ
⇒Q、なぜ黄金比は美しいのか?
…と無限に問いが続いてしまい、最終的には答えることが不可能になってしまいます。
だから結局、本質的に問いに答えることはできない。
じゃあどう答えればいいのかというと、プラトンは驚くべきことを言います。
「そこに美が宿ったからだ」
確かにこれなら矛盾こそしないものの、言い換えてしまえば「美しいから美しい」と言っているにすぎません。ただ「A=A」であることを示しただけで、実質的に解決したと言えるのでしょうか?
また、すべての問いに答えていかなければいけないのかというと、そうではないと思います。だいたい2,3回答えただけで通常相手は満足するでしょう。すべての疑問に答えること以外を解決と認めないプラトンの立場は、「数回答えれば”なぜ”を解決した」とする合意に反したものであり、「それを答えたとは言わない」「答え方を変えよう」という言語上の問題提起に終わってしまっています。
アリストテレスの四原因
プラトンの弟子である(さっきも出てきた)アリストテレスは「なぜ?」の答え方には4種類あるとしました。以下の通りです。
- 形相因(=定義を答える)
- 質量因(=材質・性質を答える)
- 目的因(=目的を答える)
- 起動因(=きっかけを答える)
実際私たちが疑問文に答えるときは、この4つどれかにほぼほぼ該当します。確かにプラトンの理屈ももちろんもっともなんです。ただし「未解明の部分を残さないように答えないといけない」と限定すると、この世のほぼすべての問いに答えることはできません。
逆にいうと全部すみずみまで説明しつくさなきゃいけない、という考えの方が間違っていると思います。あくまで常識の範囲内で答えれば原因を答えたことにはなるはずです。

まとめ&次回予告
今回は①哲学が何ではないか、そして形而上学ではないことの説明として②ベルクソンの時間論と③プラトンの考えに触れました。
読んでいた感想としては、「ツチヤ教授ひねくれてんなー」とか「言語上の問題で片づけすぎじゃね」とかその程度です。そんな考えがあったんだ、とページをめくるごとに新たな発見をして読んでいて楽しかったです。毎度毎度、新たな考えに「その通りだ!」と思ったあと、教授の反論に納得する、ということをずっと繰り返してましたね。
最後に次回予告です!
次回は4日目~7日目分まで駆け足で話していきたいと思います。内容的にはプラトン(再登場)のイデア論、現象論、デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」の範囲ですね。お楽しみに!
ということで、普段はこんな感じで読んだ本の紹介やおもしろい知識ネタを書きつけています。毎日投稿してるのでぜひ他の記事も見てください!
ではまた明日~
ツチヤ教授の哲学講義⇒ https://honto.jp/netstore/pd-book_03375161.html


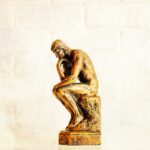

コメント 感想をください!