資本主義は素晴らしい。
と、同時に資本主義はクソだ。
いや確かに僕が豊かな生活を送れてるのも高校生でいられるのも資本主義のおかげなのだが…。けれども言わせてもらおう。資本主義は、いびつなのだ。
もし、資本主義をほんとうに信頼しているのならば、その弱みも正しく知っておくのが道理なのではないか?大事なのは、そのうえでどの思想を選ぶのか、だ。
だから今回は、資本主義のダークサイドについて語りたい。

※最後に、2つ、ハッキリさせておきたいことがある。
①僕は共産主義者ではない。
②僕は学生。学者ではない。こまかいところは飛ばして、大まかな問題提起だけを行う。
資本主義の弱点は何か
さっそく本題。簡潔にまとめると以下の通り。
①無限の利潤の追求
②使用価値と交換価値の対立
③負荷の外部化
④需要と供給のバランス
⑤豊かさの矛盾
以下、一つ一つわかりやすく解説していくつもりだ。
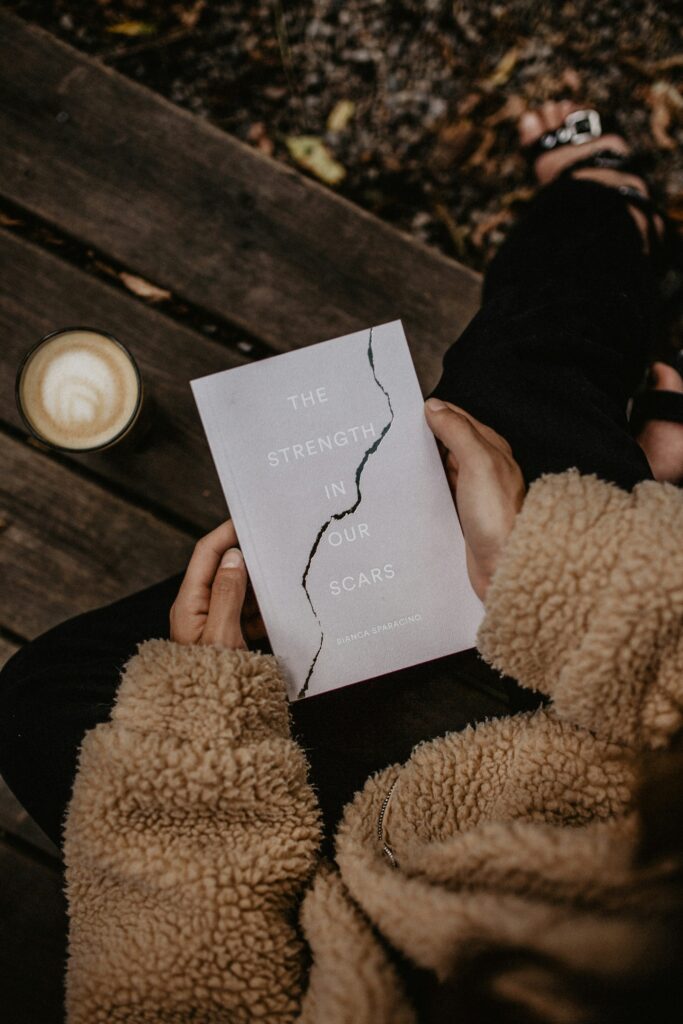
①無限の利潤の追求 ~資源は有限だけれども~
資本論において、資本は「無限の自己増殖を試みるもの」として定義されている。だけど、ちょっと考えればわかることだが、地球の資源には限界がある。鉄の総量も、自然の回復力(生物学的に言うなら、レジリエンス)も、化石燃料の埋蔵量も、有限である。
無限の成長なんてできっこない。
「いやちょっと待てよ、そもそもなんで資本主義が無限の成長をめざすことになってるの?」、こんな反論もあるだろう。
一言で答えるなら、「資本主義は、徹底した競争の世界だから」である。
企業は利益を求めることが第一の団体だ。そのためには、競合他社よりすぐれた製品、”差異”が必要だ。”差”が大きいほど、そこから得られる利益も大きくなる。企業間が競い合うことで、利益の元になる”差”が生まれては消え、生まれては消え…..、という無限の成長サイクルが爆誕する!
AppleとかGoogleとかがスマホを作り続けるのはなぜか。本来、スマホは数年は使い続けられる。だけど、頻繁にモデルチェンジが行われる。モデルチェンジは”差”を作り出す過程だ。新しい、というブランドで従来の製品と差を作り、利益を得る。もし頻繁なモデルチェンジが無ければ、「新しい」スマホは従来の製品へと埋もれてしまう。そうなったら、もはや利益は望めない。常に新しいものを作り続けること、常にライバルに差をつけ続けること。それが資本主義で生き残るためのルールだ。
結局のところ、”差”とはつまり、希少性だ。その希少性によって、需要は大きくなる。”差”を求めて競い合うシステム、それが「無限の成長」という永久機関なの。だけど、いったい、いつまでその成長が続けられるのだろうか?
利益のために他を顧みない態度は、森林を刈りつくし、大量の貧民を生み出し、気温を上げてきた。ほんとうにこれでいいのか?

②使用価値と交換価値の対立 ~実用性よりも、金~
使用価値?交換価値?少しむずかしい言葉をいきなり持ってきてしまって、もうしわけない。
使用価値とは何か。それは、商品の持つ物質的特性、実用性のことだ。例えばハサミだったら、よく切れることが使用価値だし、小説だったら、おもしろさだったり感動だったりが使用価値に該当する。
交換価値とは何か。それは、商品の持つ社会的特性、いわゆる「値段」のことだ。ハサミの値段、本の値段が、それぞれの交換価値だ。
商品はこの2つの価値を併せ持っている。
話の結末がそろそろ見えてきた。資本主義で重視されるのは、もちろん交換価値のほうだ。極端なおはなし、切れないハサミでも高く売れれば、それでよい。資本主義では、交換価値を第一におくため、使用価値がないがしろにされがちである。使用価値は交換価値の保証でしかない。
そのような実用性よりも利益を優先する態度は、よろしくない。
果樹園で、豊作だった果物を捨てるのはなぜか?
供給が需要をおおきく上回り、利益が出なくなるのを防ぐためだ。その果物を、皆に配ってあげられればよかったのにね。
廃棄される食べ物関連でいくと、「見た目の悪い野菜」なんかも捨てられがちだ。実際には見た目が悪い分、栄養が濃縮されていたりもするのだが。だけど、すべては交換価値がもっとも大事なんだから、捨てられるのも仕方がない。もったいないね。
これが資本主義の、「使用価値と交換価値の対立」という問題なのだ。

③負荷の外部化 ~白骨のうえの幸せ~
僕たちの豊かさは、だれかの不幸のうえに成り立っている。
だけどそれは、日本国内のことじゃない。不幸は、人件費や物価の安い発展途上国の人々を襲う。そして僕たちは日本にいるかぎり、そのことに気づかない。
どういうことか。
・例えば、肉類。高い環境負荷。大量の水の使用。
・例えば、鉱物。劣悪な労働環境。
・例えば、カカオ豆。カカオ豆を得るために森林が破壊され、児童労働。安い賃金の長時間労働。商品作物のための自給的農業の廃止。⇒大飢饉
このような例は無限にある。エビの養殖だってアボカドの栽培だって、なんだってそうだ。
僕たちは環境負荷を外部化しているにすぎない。
僕たちは豊かな生活をしている。しかしそれを支えているのは「周縁部」、すなわち僕たちの豊かな世界の”外側”に住む人々なのだ。彼らは、貧しい。だからリスクの大きい仕事、環境に大きな負荷がかかる仕事を、豊かな国から押し付けられるポジションにいる。その押し付けが「外部化」なのだ。
結局、「環境にやさしい製品」は、大胆な嘘、だ。
電気自動車は環境にいい? 嘘。生産国では多くの資源とエネルギーが消費されてるし、それをまかなう電力は、現地での環境負荷によってまかなわれている。
「環境にやさしい」は、「地球にやさしい」のではなく、「僕たちのいる<内側>の世界にとってやさしい」のにすぎない。
今まで述べてきたのが、負荷の外部化は”空間的転嫁”と呼ばれている。だけどこの外部化にはあと2種類もある。
”技術的転嫁”…つまり新技術によって別の資源の消費へと負荷を移しかえる方法と、”時間的転嫁”…つまり将来世代に問題解決を先送りすることで今の豊かさを維持しようとする方法だ。「大洪水よ、我が亡きあとに来たれ。」
結局、見えないだれか・なにかを使い捨てることで維持されているのが資本主義だ。それによって被害を被っているのはいったい誰なのか。よく考える必要がある。

④需要と供給のバランス ~恐慌・失業者~
恐慌も失業者も、資本主義というシステムの宿命だ。なぜか。
この2つとも、需要と供給の関係から説明できる。まずは恐慌の問題から。景気の変化は循環していることはわりと有名だろう。
①景気がよい⇒企業が生産量を上げる
②需要を上回る⇒商品の値段が下がる
③生産量を減らす⇒解雇・低賃金等
④逆に需要が供給量を上回る⇒景気がよくなる
簡略化するとこんなところか。要は景気の循環とは、需要と供給のバランスがブレることで発生するのだ。その需要と供給の不一致が最大限溜まったときに、爆発的に恐慌が発生する。
じゃあなぜ、需要と供給のバランスが崩れるのか。市場均衡価格で一致するのではなかったのか。
なぜなら、需要と供給の関係を知る過程で”ラグ”があるからだ。
企業はまず、「だいたいこれくらい売れるだろう」という、「予測」のもとで新たに商品を市場に送り出す。需要を知るためには、まず商品を市場に送りこまなければならないから。商品を売ることで、その売れ具合から、需要を推測する。だからいきなり生産量と需要がピッタリ一致することは少ない。そこで企業は、あとから生産量を調節する。
が、しかし。この売れ行きを見て生産量を調節するには、長い時間がかかる。だから、生産量を調節するための予測を外したら、一気に売れ残りができることがある。そーして需要と供給のバランスが急速に崩れる。不況はだいたい、この「先に生産、あとから調節」の仕組みが犯人ってこと。
お金は、空想つきの紙切れだ。恐慌は、空想がハジけて、お札がただの紙になることで発生する。
近年はいわゆる信用取引によって、個人が実際に持っている額の、何倍ものお金を動かせるようになった。その結果、破産したり支払いが滞ったりしたときの影響がデカくなって、信用を前提としたシステムが一気にマヒしてしまったりする。「後払いだったら、後で必ずお金を払ってくれる。」「お金を貸したのだからあとで帰ってくる。」そうした約束ごと(信用)が破られた結果、いろんなシステムが一気に破綻してしまうのが、恐慌である。
そして、失業者。資本家にとって、失業者はいなければならない。
失業者=労働者予備軍、だ。失業者がいる=労働者にいくらでも替えがいる。だから、労働者は安価で劣悪な労働条件で働かなくてはいけない。コレって、お得でしょ?
そして、失業者は必ず生まれる。”資本の有機的組成の高度化”。企業は利潤と競争力を高めるために、生産方法を最適化していく。人が機械に置き換えられたり、余分な労働者を解雇したり。だから競争がある限り、失業者は絶対にうまれ、完全雇用はありえない。(あるとしたら、競争のない共産主義社会だ。)

⑤豊かさの矛盾 ~GDPは上がるけれども、~
まず、本質的な話をしよう。(すこし難しいかも!)
どうやって豊かさを生み出すのか。
資本主義は、需要と供給の「差」から利潤を生み出すシステム。言い換えると、需要を供給に置き換えて、そのプロセスでお金を回収するシステム。
「欲しいと思っている人」に、商品を渡す。そしたら「すでに持ってる人」が増える。供給が増えて、需要が減る。最後、皆が「すでに持っている人」になったら需要はなくなっちゃう。
と、いうわけで、最初は需要と供給の差が大きい状態で始まる。始めなければならない。
この需要と供給の差を名付けるならば、希少性、が適切だろう。
まとめる。モノの希少性が大きいとき。つまり、モノが独占されてるとき、需要と供給の差は大きい。ここからスタートして、希少性を解消するために、取引が行われる。取引を通じてモノが行き渡り、モノの希少性は失われていく。同時にお金が1ヶ所に集められていく。これが売ること・買うことの本質だ。
じゃあ利益を得たいなら、どうやって希少性を作りだすか、だ。この「差」の作り出し方は、2通りある。
①新しく商品を生産することで差をつくる方法。新型テレビとか新作ゲームとか米とか小麦とか。商品の生産▶所有(独占)▶希少性、の流れ。
②すでにある物を独占して希少性を生み出す方法。たとえば、自由財。水や空気などの無料の資源のこと。これらはありふれてて、どこにでも存在するため希少性がない。しかし自由財を独占すれば、資源は偏在することになり、希少性が生まれる。商品化できる。
問題は②の方法。水や空気が独り占めされたら、皆の生活は貧しくなる。だけど、それらに値札がつくことで計上れる取引量は増える。GDP的には、社会は豊かになる。これが豊かさの矛盾だ。
そしてこれは机上の空論ではない。実際に今では水がペットボトルで販売されるようになった。もっと遡れば、もともと誰のものでもなかった土地が、今では不動産投資の対象となっているじゃないか。
皆のものを、個人が占有することで、社会全体は「豊かに」なる。だけど、それは本当の意味での豊かさなのか。資本主義のいう「豊かさ」と、僕たちの知っている豊かさは、あくまで別のものなのだ。
うわべに騙されないように!

まとめ
と、いうことで!!
今回は久しぶりのガチ考察でした。最近経済について学んだ事柄を全部、書きつくしました。僕たちにとっては、あまりに深くなじみすぎていて、その悪いところに気づきにくくなっている資本主義の裏側。キッチリご理解いただけたでしょうか。

今、時刻は0:00を回ってます。明日学校もあるのにめっちゃ眠いです。では。おやすみなさい。
グッド・ナイト!!



コメント 感想をください!
マルクスが150年前に予言した、資本主義崩壊が現実になってきていますね。
マルクスの著書、「資本論」第1巻の最後近くで資本主義から未来社会へいたる道はどう考えられているか語られています。
「資本主義的私的所有の終わりを告げる鐘が鳴る」という文の後で、次のような有名な文章が書かれています。
資本主義的な生産様式から生じた資本主義的な取得様式は、それゆえ資本主義的な私的所有(Privateigentum)は、自分の労働にもとづく、個人的な私的所有の第1の否定である。しかし、資本主義的な生産は、ある自然過程の必然性によって、それ自身の否定を生み出す。これは否定の否定である。この否定は私的所有を再建することはしないが、しかしたしかに、個人的な所有(das individuelle Eigentum)を資本主義的な時代の成果──すなわち、協業や土地(Erde)および労働そのものによって生み出された生産手段の共同占有(Gemeinbesitz)──にもとづいて再建する(マルクス『資本論』第1巻)。
つまり、2つの否定(①と②)によって、資本主義以前と以後との3段階をどう性格づけるか、という問題です。
マルクスが未来社会について示唆している数少ない場所ですが、そのときヘーゲルの二重の「否定」という概念を使いながら、生産や所有、占有という言葉によって説明しています。
資本主義で進んだ商品化をやめ、再びコモン(ありふれたもの)にしようというのがマルクス晩年の思想ということです。
※注意して欲しいのは、コモンを動かす「コミュニズム」は、あくまでもシステムであって、属人的なものではないということ。
↓以下へ続く
以下、デヴィッド・ハーヴェイ著の
「資本主義の終焉」から引用↓
(本書は、資本の動きをめぐる矛盾を17に整理して、原理的・歴史的に分析し、さらにそれをもって21世紀資本主義の未来について考察するものである。「第Ⅰ部 資本の基本的な矛盾」、「第Ⅱ部 運動する資本の矛盾」、「第Ⅲ部 資本にとって危険な矛盾」で構成されている。)
個人的な感想としては、私的所有・契約・法的人格(著者はそう言う言葉は使っていないが)と言う近代市民法の制度的プラットフォームをしっかりと捉えた上での、資本主義理解だと感じる。
「第Ⅱ部 運動する資本の矛盾」の文から引用↓
私たちの眼の前で起きて来たこと、起こりつつあることの分析になる。
「技術変化は犠牲や苦痛を必ず伴うものであり、しかもその犠牲や苦痛が平等に分担されるわけではない。常に問かけるべき問題は、創造から利益を受けるのは誰であり、破壊の矢面に立たされるのは誰なのか、である。」(本書138頁)。このような現象が、世界的な規模で展開されて行く現実。
「第Ⅲ部 資本にとって危険な矛盾」は、本書の結論と言うことになる。「あらゆる資本家がプラス利潤を実現するには、開始時点にあった価値が一日の終わりにはそれ以上の大きさになっていなければならない。」(本書306頁)。
ゼロ成長が続けば資本主義の弔鐘が鳴ることになるとする。だが、「ここに市場の失敗と言う問題が存在しており、さまざまな国家介入や補修的課税や規制措置の大義名分もここにある。この点は右翼の経済学者でさえ認めている。」(本書335頁)。
結論↓
「資本主義は、“資本”という経済エンジンによって動いている。そして最終的には資本主義の宿命である暴力的調整が続くのかもしれない…。」
また、資本主義は、AIとは切っても切れない関係だということは、理解しておくべき。
それはまた次回。ここで一旦今日は区切ります。
遊ろぐさん、雨お互い気をつけましょうね
流石。もう、さすがとしか言いようがない。
1つ目のコメントはいわゆる「否定の否定」の箇所ですね。僕も”そこだけは”辛うじて読めました。苦笑。
資本論が難しすぎる。解説の本はいくらか読んでるけど、いつかはオリジナルを読みたい!!
「資本主義の終焉」ですか…。ふむふむ。初めて聞きました(無知)。
17の矛盾か。負けました。
実はこの記事を書くきっかけとなったのが「人新生の資本論」ていう本なんです。(ほんなさんだったら、もしかしたら読んだことがあるんじゃないかな?)。それ以前からマルクス経済学に少し興味があって、ちょっとは読んでました。「いつか本格的に、資本主義とか社会主義とかについて文章を書きたい!」って意気だったけど、それを理論的な一貫性をもって書ききるほどの知識も持久力も無い!…ということで、表層の現象をすくってこれを書いたまでです。だからこの記事は、原理的な考察が全然なってない。こればっかりは、欠陥ですね。
まあ不完全でもいいから書いちゃえ!っていうのが、このブログの方針ですからね。ちょっと言い訳。
「雨気をつけて」と言われて、こう返すのもどうかなと思うですけど、実は雨好きなんですよね。手荷物さえ無ければ、雨のなかにかけだしたいくらい。
ほんなさんは雨(あと台風)に気をつけてくださいね!