今さっきちくま読んだので、頭の整理がてら私が理解したことを書いていきたいと思います。
ぜひとも、先にちくま評論の方を読み自分なりの考えを持ってから、こっちを読んでほしいと思います。(あくまで私なりの解釈なので正しいとは限りません。間違ってたらごめんなさい!)
本音を言うと、さすがにブログを放置しすぎてる感に駆られて書いています。
東京タワー
この文章は東京タワーの立っている土地についての問いかけから始まります。増上寺の裏手、不気味な印象を与え「死霊の気配を感じさせる」東京タワー。ここは何か特別な土地だったのではないのか?
そして筆者はかつてそこに古墳群があったことを知ります。昔は海に突き出ている半島で、現実世界と感覚を超えた超越的な世界との境界(=古語で「サッ」と呼ばれていた)であり、聖地だったのです。そして時代を経てもそこは死霊の世界との接触地域と考えられ続け、後に東京タワーが建設されます。
東京タワーはエッフェル塔を意識して作られましたが、それぞれの意味は異なり、本文中では対比されています。エッフェル塔は明確に「天と地をつなぐ橋」であり、神と私たちを媒介する存在です。それに対して東京タワーは「天」では無く、どこかにある超越的な領域と私たちをつなぐ橋なのです。そして東京タワーは、エッフェル塔が天界と私たちという明確に区別された2つの領域を繋ぐのに対して、明確に区別できない超越的な領域(=死の領域)と私たちを繋ぎます。さらに筆者は過去と未来まで繋いでいると言います。
最後の段落ではまとめとして、農夫からパリを見ると神秘的に見えることを引き合いに出し、私たちは縄文人の野生の思考で東京を捉えると良い、と書かれています。
そしてここからが私の解釈になるのですが、まず東京タワーとは何なのか、ということについて考えました。幾度も例が出てきたのでそれをまとめると、いずれも「私たちのいる現実の世界と超越的な世界を繋ぐ存在の象徴」ということを言っています。
この構造を分かりやすく示すと、文明的な存在(私たち)と本能的、非現実的な存在(死者の領域)が共に存存しているということを、1つの具体例として東京タワー(文明的なもの)が増上寺の裏手(死者の領域との接点)にあることと関連付け、私たちのなかにもまだ縄文人の野生の思考・超越性が生きていることを示しています。
また東京タワーが過去と未来を繋ぐというのも、今説明した通り、私たちに備わっている本能的な超越性の思考(縄文人の野生の思考)が時代を通して生き続けていることを示したのだと思われます。
この超越性ってのはいわゆる霊感的なものなのかな…?
グーグルマップの世界
最近、私たちと地図の関係が変わりつつあります。かつて地図は「見渡す地図」であって、広い世界に、社会に、外に目を向けるものでした。しかし今ではグーグルマップのような「導く地図」によって、私たちの目線は内側へと誘導され、「見渡す」ことが無くなりつつあると筆者は言います。つまり私たちの見る世界はどんどん縮小しているということです。なぜ?
それはグーグルマップがあらゆる地図情報を並列に配置することによって、人々が自分にとって有用な、自分を中心とした地図のみを選び出すようになるからです。また「導く地図」は目的地までの移動のアシストに特化していて、コンピュータやGPSを使い、ユーザーは現在地と到着地の2点を追うだけになります。またユーザーは地図の視点の変化や、現在地の追跡により地図を自分のものにしていき、「見たいものしか見ない」態度ひいては各個人の極端な意見を強化します。
これらの現象は一言で「個人化」と表せます。
地図を介して「社会」を想像しなくなることで、私たちの視野は「いま・ここ」だけの狭さに制限されます。「見たいものしか見ない」ことにより、そもそも私たちは社会を見ようとする(ズームアウトする)ことがなくなり、代わりに自分自身にのみ大きな関心を払う(ズームインする)ようになってきています。
このようにグーグルマップは私たちと地図の関係を変えてきています。私たちもグーグルマップに支配され、社会を見ないように誘導されていませんか?
…というのが本文です。結構まとめるのに時間かかったし、私の意見も混ぜて書いたのでこの文はこれまで。新しい技術(グーグルマップ)の裏で失っているもの(社会への意識)に気づくことが大切ってことですね。
「誰か」の欲望を模倣する
この文のテーマは、私たちが自分の欲望と思っているものは実は他人や社会にとっての欲望で、私たちは本当の主体ではないのではないか、ということです。
人がなにかに夢中になり熱狂したりするとき、例えばスターに熱狂しその人の勧めた物を買ったとき、それはあなた自身の欲望では無くスターを模倣したにすぎないです。同様のことは人が何かを欲する時、それは誰かを模範にしているだけ、といった風にも言えます。だから私たちの欲望は「他人を媒介して」物に向かって言っているといえます。
このとき私の欲望を介する他者は、一般化すると世間や社会(の一部)になります。そして私たちは世間と同じでいたいという欲によって世間を模倣し、世間の望むものを「自分」が得たいと思っているのだと錯覚しています。(スターの例だと、私はスターのようになりたいという欲によりスターを真似して、スターの持っているものを自分が欲しいと思っているのだと錯覚します。)
こうして人は社会を手本とした模倣をすることで社会を鏡として、また「私」自身も他人や社会にとっての欲望を反映するという意味で「社会の鏡」になります。こうして欲望は無限に反射し合っているのです。(つまりある人が他人を真似るということが無限に連鎖している)
そもそも「主体的」を外国語で表現すると、従属や臣下といった意味が伴われます。なぜなら主体は与えられた役割・ルールを遂行するだけの存在だから。そしてさらに言うと、欲望の主体は私たち自身ではなく、むしろ私たちを遂行へと駆り立てる「社会」が主体となっています。それは私たちに意識されることで、私たちの欲望を規定しています。
結局、私は鏡のなかに理想のモデルを投影し、モデルを模倣することで、従属者として「主体化」されるのです。
うーん、表現するのが難しい。
例えば私は以前から「あたまよくなりたい!」って思ってましたが、それなんかも社会で賢い人材が欲されているから、お手本となる人物像をトレースをしているだけにすぎない、と言えますね。
そうして私が賢くなる(!?)ことで、今度は他の人の模範像を作り上げていく…的な?
多分こんな感じです。
まとめ
私も現代文は昔から苦手だったけど、なんとか分析して書きました。後期中間で少しでも役に立てば幸いです。頑張れ!
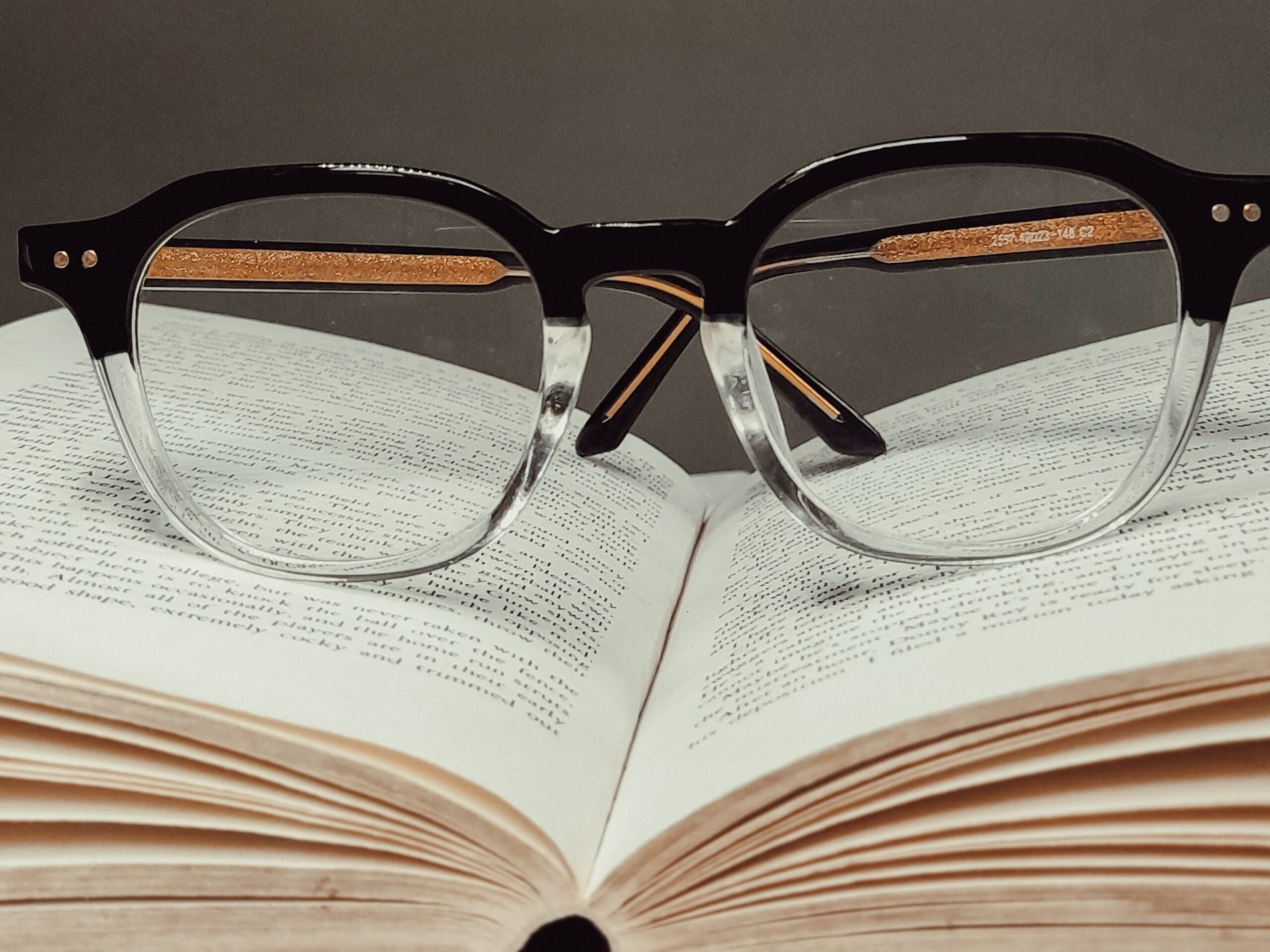

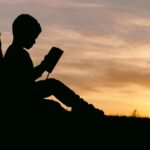
コメント 感想をください!